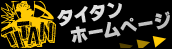このコラムは、タケタリーノ山口が己の魂の叫びを2003年に書いていたものです
実に久し振りに”負け犬の遠吠え”を書いてみた。
なぜ、しばらくの間、書いてなかったのかというと、単純に文章を書くのが面倒臭かったからだ。
そして今、書いてる最中も面倒臭いと思っている。
では、なぜ俺はまた書き始めたのか・・・・・。
文字と句読点が奏でるデリケートな世界へと身を投じたのか。
先日、俺は高校時代からの友人である I という男と飲んでいた。
すると、なぜかこの”負け犬の遠吠え”の話題になった。
友人 I 「お前最近コラム書くのさぼってるべ」
俺 「は?さぼってねぇよ。ただ、書くのが面倒臭くなっちまっただけだよ」
友人 I 「それをさぼってるって言うんだろーが。世間では」
俺 「お、するどい」
友人 I 「いいか、何事も続ける事に意味があるんだよ」
俺 「お前は継続は力なり促進委員会の会長さんか」
友人 I 「世の中面倒臭い事なんて、たくさんあるんだ。その他の面倒臭い事に比べれば、コラムを書く面倒臭さなんて、たいした事ねぇだろ」
格好良かった。
友人 I が大人に見えた。
ただ、俺にはコラムを書く面倒臭さを上回る程の面倒臭い事がなかった。
結局、俺はコラムを書く面倒臭さなんてたいした事ないと思う事はできなかった。
その後、俺達は俺の家に移動し、飲み続けた。
酒好きの友人 I は、かなり上機嫌だった。
友人 I は、寝ようとする俺を強引に起こし、飲み続けた。
友人 I は、友人 I の布団を敷いている俺をつまみに飲み続けた。
ベロベロだった。
気付けば友人 I はベロベロに酔っていた。
それでも友人 I は、クソミソに飲み続けた。
いや、まるでクソのように飲み続けた。
汚かった。
汚い飲み方だった。
ティッシュで拭いてしまいたくなる程の有り様だった。
面倒臭かった。
面倒臭い飲み方だった。
そう、コラムを書くより面倒臭い有り様だった。
コラムを書く面倒臭さなんて、たいした事ないと強く思えた。
その時、俺は思った。
友人 I は、俺にコラムを書かせようと、あえて自分自身で面倒臭い奴を演じてくれたのではないか・・・。
友人 I は、自分自身がクソのようになりながらも、俺を応援してくれているのではないか・・・。
俺は、友人 I の友情に心が熱くなった。
ふと気付くと、友人 I は、すでに布団の中でクソのように寝ていた。
俺は、そのクソの上で、ありがとうとつぶやいた。
俺は普段テレビドラマを見る事がほとんど無い。
なぜなら、俺は自分自身の人生のドラマを作るのに精一杯だからだ。
そして、もちろんエンディングはハッピーエンドって決めてるんだバカヤロー。コノヤロー。
そんな事はいいとして、俺は最近「元カレ」というドラマの再放送にハマっている。
軽く内容を紹介すると、堂本剛が主人公で、その「元カノ」役が広末涼子。
そして「今カノ」が内山理名というキャスティングで、「元カノ VS 今カノ」の様子を見せつつ、堂本剛の本当の気持ちはどうだ?みたいな甘々なラブストーリーだ。
俺は不思議とこの甘々なラブストーリーにハマり、次の展開をワクワクしながら見守っている。
もし、これがドラマではなく本だったら、最後のページから読んでしまいたいくらいだ。
いや、逆に結果を知るのが恐くて読まないかもしれない。
それ程ハマっているのだ。
しかし、何故俺はこのドラマにそれ程ハマっているのか?
俺は必死で考えた。
はっきり言ってドラマを見る間も惜しんで考えた。
すると、意外なことが分かった。
俺はドラマにハマっているのではなく、堂本剛にハマっていたのだ。
そう、ドラマが見たいのではなく、堂本剛という男が見たいのだ。
俺は今まで何の意識もなく、一般的なタレントとして堂本剛を見てきた。
しかし、「元カレ」で見せる堂本剛の顔は、役柄上の事とはいえ、とても穏やかで、無性に俺を惹き付ける。
全く害の無い人柄だ。
そう、人として無害だ。
そして、何と言っても「元カノ」や「今カノ」に接する時のカドの立たないソフトな感覚が実に魅力的だ。
そう、とてもソフトタッチなのだ。
いや、ソフティーだ。
彼女達にしてみれば、多い日も安心なはずだ。
実にサラサラだ。
ナイトギャザー付きだ。
とにかく、俺は堂本剛が好きになってしまった。
Likeではなく、Loveだ。
できれば、彼のハートを射止めたい。
これは彼女達への宣戦布告だ。
「元カノ VS 今カノ VS タケタリーノ」だ。
いや、
「元カノ + 今カノ VS タケタリーノ」でもいい。
ナイトギャザー付きだ。
俺はやる気だ。
俺は自分自身の人生のドラマのエンディングを堂本剛と迎えてもいい。
ハッピーエンドだ。
それこそ本物のドラマだ。
俺は「元カノ」を見る間も惜しんで、空想の世界へ没頭した。
これは、俺が高校生の頃の話だ。
俺は今でこそ「燃える男」とか「魂の塊」とか「炎のオブジェ」などと言われ、「熱い男=タケタリーノ山口」というイメージが浸透しているが、その当時の俺は、何をするにも、熱くもなく、冷めてもなく、常に一定の体温を保っているように見えるということで、「平熱」と呼ばれていた。
およそ、36.2℃ぐらいの感覚だったのだろう。
いたって普通の状態だ。
しかし、周囲の人間からは「平熱」と呼ばれ、普通の状態に見えていても、俺なりに必死になってもがいている時期だった。
そう、実は俺は死に物狂いで生きていたのだ。
では、なぜ周囲の人間は、死に物狂いで生きていた俺を「平熱」などと呼んでいたのか?
そう、なぜなら、当時の俺は、人に必死な姿を見せることが格好悪いことだと考えていたのだ。
だから俺は、いつも淡々と、あえて淡々と、涙そうそうと「平熱」の状態を作り出していたのだ。
今思えば、俺は必死になって生きていたのではなく、この「平熱」という状態を作り出すことに必死になっていたのかもしれない。
そんなある日、クラス対抗のマラソン大会があった。
この大会は、20kmのコースを各クラスの代表5人が走り、その5人の合計タイムが一番早かったクラスの勝ちという大会だった。
俺は何があっても普通の状態でマイペースに走り続けるだろうという事で推薦され、代表として走る事になった。
そして、運命の時が来た。
パーンというスタートのピストル音と共に一斉に飛び出す各クラスの代表。
普通の状態でマイペースな俺。
汗を飛び散らせて走る各クラスの代表。
普通の状態でマイペースな俺。
嗚咽のような声をあげながら走る各クラスの代表。
普通の状態でマイペースな俺。
そして、何と、恐るべき数値がはじき出された。
3km、6km、9km、12kmと3km間隔で計測されるタイムがほとんど同じな俺。
あまりにも同じリズムで一定の速度を保ちながら走る俺に、観戦していたクラスメートから声が上がった。
「メトロノームだ」
「メトロノーム走行だ」
俺はリズムを一定に保ち続ける。
沸き上がるクラスメート達。
寸分の狂いもない。
しかし、忘れないでほしい。
俺は必死で生きていたのだ。
必死な姿を人に見せるのが格好悪いことだと思っていたから必死で「平熱」の状態を作り出していたが、俺は必死で走っていたのだ。
今思えば、同じペースで走り続けることに必死だったのかもしれないが、とにかく必死で走っていたのだ。
その俺に対して、「メトロノーム」って!!
俺に怒りが芽生えた。
そう、俺は熱くなった。
俺はとにかく熱くなった。
周囲の人間からすると、熱が出た感じだ。
「平熱」から熱が出た感じだ。
しかも、高熱だった。
ある意味、ひどい病気だった。
その時から現在まで、俺は何故かずっと風邪気味だ。